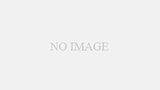2月7日の午前中に東京駅付近で用事があったため、終わった後に上野まで行き、国立西洋美術館で開催していた『モネ 睡蓮のとき』を見てきました。
今回は、その記録や自身の学びになった部分を書いていきたいと思います。
私自身は美術の初心者のため、ためになることは書けないと思いますが、
記録:当日の流れ
モネ展は本日(2月11日)までの開催なので、私は終盤に行ったことになります。
私は当日の14時半ごろに上野に到着して、そこから当日券購入のため並びました。
購入までに1時間ほど待ち、購入後も入場開始の18時まで空き時間があったため、科学館のほうにも行きました。(そちらは別記事で書いていきたいと思います。)
17時半ごろに入場開始の列に並ぶ形になりました。美術館に入場後、ロッカーに荷物を預け会場に入りました。
常設展も見たため、建物から出たのは20時過ぎになってしまいました。会場の外はライトアップされていて、昼に見る姿とはまた違った印象を受けます。

記録:購入したもの
購入したものは以下の通りです。
- 図録『モネ 睡蓮のとき』
展示を見終わった後はショップでの購入がありますが、長い列になっていたためグッズ等の購入はしていません。ですが、図録に関しては、スタッフに声をかけると別の列に案内してくれるため、そちらを購入して会場を出ました。
図録で確認したところ、モネ展に関しては、東京の後は京都と愛知で開催されるようなので、機会があればぜひ行ってみてください。
記録:展示を見ての所感
個人的な所感になってしまいますが、近づきすぎると何が書かれているかわからないため、少し離れてみることがおすすめです。展示されていた作品には、大きいものもあります。大きな作品に関して(そうでないものに関してもですが)は、近づいて見るだけでなく遠くから見ることで全体を把握できると感じました。
私は見方を選ぶことはできますが、モネはかなり近い距離で書いていたはずなので、どうやって書いていたのかといった疑問を持ったりしました。
学び:関連することを調べてみた
以下に展示に関連することを調べてみたことを書いていきます。
そもそも、何も知らない状態で見に行っているため、まずは知ることから初めてみました。簡単に調べてその結果をまとめています。
以下が調査項目です。
- 「印象派」について気になった部分
「印象派」について気になった部分
そもそも印象派についての知識が全くなかったため、そのことを調べることから始めました。
印象派とは何か、なぜ印象派と呼ばれているかといったことは、様々な媒体に書かれているため、特に書くことは行いませんが、一つどうしても気になることがありました。
印象派と呼ばれる人々は、最初は専門家に受け入れられていなかったということが書かれています。以下にウィキペディアの「印象派」からの引用を記載します。
批評家や権威者が新しいスタイルを認めなくても、最初は敵対的であった人々までもがだんだんに、印象派は新鮮でオリジナルなモノの見方をしていると思い始めた。細部の輪郭を見るのではなく対象自体を見る感覚を取り戻し、さまざまな技法と表現を創意工夫することで、印象派は新印象派、ポスト印象派、フォービズム、キュビズムの先駆けになった。
「印象派」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://ja.wikipedia.org/)。2025年2月11日15時(日本時間)現在での最新版を取得。
さて、認められなかった新しいスタイルとは何だったのでしょうか。
書籍『美術の物語』によると、キーワードは『モティーフ』で、ウィキペディアの上記引用部分の「細部の輪郭~~」という部分が該当しそうです。
以下に『美術の物語』より引用したいと思います。
完成とは言い難い一見ぞんざいなこの筆使いは、よく批評家たちの腹立ちの種となった。
エルンスト・H・ゴンブリッチ 著.小野寺優 発行.「美術の教科書」.株式会社河出書房新社,2019,p.518
それまで画家たちは、「絵のような」とだれもが認める自然の一場面を見つけてくるものとされていた。
エルンスト・H・ゴンブリッチ 著.小野寺優 発行.「美術の教科書」.株式会社河出書房新社,2019,p.519
印象派の人々は、外に出て自然の移り変わりなどを絵に反映させることをしていたため、それまでの絵とは異なる技法を使っていたようです。
そして、過去の絵とは異なる場面だったことも専門家に受け入れられない理由となったようでした。
私が感じた、少し離れて見ることで全体像が把握できたという感想は、自然の移り変わりを絵に反映させることで発生した、当時はぞんざいと言われてしまう筆遣いが理由なのかもしれません。
ですが、実際に見てみるとモネの作品がなぜ評価されたか感じることができるかと思います。
東京からは移動してしまいますが、まだ日本で作品を見ることはできるので、ぜひ直接自分の目で見ることをお勧めします。
まとめ
今回は、モネ展に行ってきた記録と、気になったことを調べたことを書いてきました。
実際に見ることで、どのような印象を受けるかは個人で異なります。実際に見ることでの印象を、これからも大切にしていきたいと思います。そしてそこから生まれた疑問も、しっかりと調査してそのことについて知っていくことをしてみたいと思います。
今後も、展示に行った際は、その記録をしていくかと思います。ぜひまたお読みいただければ幸いです。
今回は、ここまでとなります。お読みいただき、ありがとうございました。